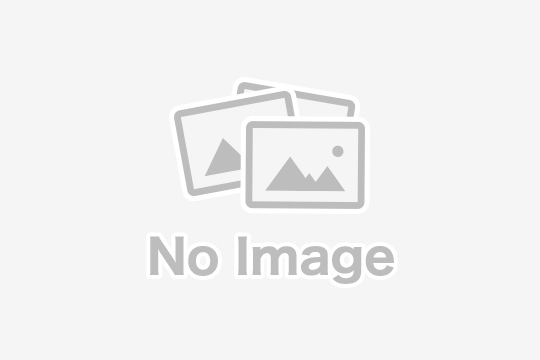この記事は約 6 分で読めます。
こんにちは、めしラボです。
鉄フライパンを使い始めるためにはシーズニング(油ならし)をしなければいけません。シーズニングとはフライパンに油をなじませて油膜(樹脂皮膜)を形成させることです。これにより「食材がくっつく」「サビてしまう」などの問題が起こりにくくなります。
鉄フライパンを上手に使うためには、油膜を知ることが大切です。
 めしラボ
めしラボ今回の記事は次のような人におすすめ!
- シーズニング(油ならし)の目的は?
- 油膜(樹脂皮膜)の正体は?
- シーズニングに適した油脂の種類とは?
油膜の正体は重合した油脂です。
鉄フライパンには表面加工が施されていませんので、食材と金属面が直接触れ合うことでくっつきやすくなります。そのため油脂を酸化重合させることで形成される油膜(樹脂皮膜)を利用することで、食材と金属面が直接触れないようにしていきます。
シーズニングのためにオーブンで焼いたりくず野菜をいためたりするのは油脂の重合を促すためです。
スポンサーリンク
油膜の正体は油汚れ?
油膜は油脂が重合することで形成されます。
調理や健康面では敬遠されている油脂の酸化重合反応ですが、鉄フライパンなどを使いやすくするためには積極的に利用されています。油脂の酸化重合というのは油脂の劣化そのものですので「油膜=頑固な油汚れ」といっても過言ではありません。
脂肪酸の自動酸化は高温により加速します。
脂肪酸が加熱されると脂肪酸内の二重結合が移動して共益結合となり、その後に他の脂肪酸とつながって橋渡し結合が発生します。この重合は通常の調理時にも発生していますが高温に熱すると加速度的に進むことになります。
そのため「オーブンで焼く」「くず野菜を炒める」などの手段がとられます。
シーズニングにおすすめの油脂とは?
油脂の種類により油膜の性質が変わります。
食用油脂に含まれている脂肪酸は、アルキル基にカルボキシル基が結合したものです。二重結合部は容易に酸素と結合して酸化反応が進みます。生成した過酸化脂質は分解されて低分子のカルボニル化合物となり、さらに酸化が進むと酸素原子を介して架橋が形成されて重合物となります。
そのため脂肪酸の二重結合の数がポイントになります。
| 二重結合の数 | 相対酸化速度 | |
|---|---|---|
| ステアリン酸 | 0 | 1 |
| オレイン酸 | 1 | 100 |
| リノール酸 | 2 | 1200 |
| リノレン酸 | 3 | 2500 |
ここで指標になるのがヨウ素価です。
ヨウ素価は二重結合(C=C結合)の数(油脂を構成する脂肪酸の不飽和度)を示す数値であり、その値の大きさによって「乾性油(ヨウ素価130以上)」「半乾性油(ヨウ素価100~130)」「不乾性油(ヨウ素価100以下)」に分類されています。
ヨウ素価が大きいほどに重合しやすく乾きやすい油脂であるということです。
| 乾性油 ヨウ素価130以上 | アマニ油、胡桃油、ヒマワリ油など |
|---|---|
| 半乾性油 ヨウ素価130から100程度 | コーン油、胡麻油、大豆油など |
| 不乾性油 ヨウ素価100以下 | オリーブ油、椿油、菜種油など |
油脂の種類は油膜の性質に影響します。
たとえばヨウ素価の高いアマニ油(168~190)で作られた油膜には「短時間で硬くきれいな油膜が形成される」「割れやすい」などの特徴があり、ヨウ素価の低いオリーブ油(75~94)で作られた油膜には「柔らかく粘度の高い油膜が形成される」「十分な油膜の形成には時間がかかる」などの特徴があります。
これらのことからも、個人的には「グレープシードオイル(128~150)」「ハイリノールタイプのヒマワリ油(136~148)」「大豆油(124~139)」「なたね油(94~126)」あたりから好みに応じて選ぶことをおすすめしています。
もちろんオリーブ油を使うことが間違いというわけではありません。
油脂の種類による使い方の違いとは?
油膜の性質により扱い方が変わります。
ヨウ素価の高い油脂(アマニ油など)で形成された油膜には「艶があり美しいが硬く割れやすい」などの特徴があり、ヨウ素価の低い油脂(オリーブ油など)で形成された油脂には「粘りがあり割れにくいが使いやすくなるまでに時間がかかる」などの特徴があります。
そのためシーズニングや扱い方にも違いが生まれます。
- ヨウ素価の高い油脂:耐摩耗性に優れ、靭性の低い油膜になる
- ヨウ素価の低い油脂:耐摩耗性に劣り、靭性の高い油膜になる
どちらが良いかは好みの問題です。
耐摩耗性と靭性(粘り強さ)は反比例の関係にありますので、ヨウ素価の高すぎる油脂を使えば「極端に衝撃に弱く剥離しやすい油膜」になりますし、ヨウ素価の低すぎる油脂を使えば「油膜が形成されにくく心が折れやすくなる」ことになります。
これらのことからも、個人的には大豆油(124~139)や菜種油(94~126)などのように比較的半乾性油に近いヨウ素価の油脂を好んで使っています。
はじめてのシーズニングであれば半乾性油から乾性油に分類されている「グレープシードオイル(128~150)」「ハイリノールタイプのヒマワリ油(136~148)」「大豆油(124~139)」などで試してみることをおすすめします。
樹脂皮膜を壊さないための注意点とは?
油膜は極端なpHの偏りを嫌います。
多くの金属は酸と反応します。これは鉄フライパン(鋼鉄)も例外ではなく、酸性の強い食材を調理してしまうと酸と反応して油膜や酸化皮膜が剥離してしまうことがあります。油膜や酸化皮膜が剥離してしまうと料理にも影響します。
またアルカリ性にも注意が必要です。
鉄は両性金属(アルミニウム、亜鉛、錫、鉛)ではありませんのでアルカリ性には反応しません。しかし油膜の正体は頑固な油汚れのようなものですので、油汚れがアルカリ性洗剤で落とされるように油膜が落ちてしまうことがあります。
クレンザーや重曹にも注意が必要です。
クレンザーのモース硬度は7、重曹のモース硬度は2.5です。対して鋼鉄のモース硬度は5、油膜は不明ですがフッ素樹脂(テフロン)のモース硬度が2であることを考えると、それ以下であると考えるのが妥当かと思います。
このことからもクレンザーや研磨剤としての重曹は油膜を傷めます。
まとめ・鉄フライパンの油膜とは?
鉄フライパンは油膜により使いやすくなります。
油膜とは油脂が酸化重合することで形成される樹脂層(ポリマー層)のことであり、シーズニングに使用された油脂の種類により異なる性質の油膜が形成されます。最近はヨウ素価の高い油脂を使用した硬質の油膜が好まれる傾向にありますが、最終的には好みの問題です。
鉄フライパンのシーズニングは何度でもやり直せますので、色々と試してみることをおすすめします。
おすすめの関連アイテム
厚板フライパン 極(リバーライト)
- 材質:
- 鉄(特殊熱処理)
- 板厚:
- 3.2mm
- 重量:
- 0.83kg
リバーライトの厚板タイプです。
特殊熱処理(窒化処理)が施されていることに加え「3.2mmの厚板仕様になっている(通常タイプは1.6mm)」「木製のハンドルが採用されている」などの特徴があります。これにより「耐摩耗性や耐食性に優れる」「酸化皮膜を形成させる必要がない」「熱容量が高いことにより料理の仕上がりが良くなる」「ハンドルが熱くならない」などのメリットが得られます。
管理人のレビュー
特殊熱加工が施されていることに加え「一般家庭の台所においても違和感のないデザイン」が気になっています。現在使用している鉄フライパンはデバイヤーですが、機会があれば使いたい(切り替えたい)と考えています。
IH対応鉄フライパン(デバイヤー)
- 材質:
- 鉄
- 板厚:
- 2.5mm
- 重量:
- 1.38kg
デバイヤーの定番鉄フライパンです。
盛り付けをしやすいハンドル角度とデザインの良さが魅力の鉄フライパンです。高品質な厚板の鉄が使われていることもあり、安価な鉄フライパンと比べると格段に使いやすい(食材がくっつきにくくサビにくい)仕様になっています。
管理人のレビュー
デザインの良さが気に入って使っています。しかしデバイヤーの特徴ともいえるハンドル角度には「蓋が干渉してしまう」というデメリットもあります。お使いの蓋の流用を考えている場合には注意が必要です。
打出し 鉄 フライパン(山田工業所)
- 材質:
- 鉄(打ち出し)
- 板厚:
- 2.3mm
- 重量:
- 1.25kg
山田工業所の定番フライパンです。
通常の鉄フライパンはプレス(圧力を加えて成型する方法)などで作られていますが、山田工業所の鉄フライパンは打ち出し(たたいて成形する方法)で作られています。これにより鉄の分子が詰まり、硬く粘りのある性質を持つようになります。
管理人のレビュー
機能性を重視するのであれば山田工業所の打出し鉄フライパン一択かと思います。事実、多くの飲食店では山田工業所の鉄フライパンや中華鍋が好まれています。デザインが好みで台所の印象と合うのであれば心からおすすめできます。
竹ささら(遠藤商事)
- 材質:
- 竹
- 長さ:
- 235mm
- 重量:
- 105g
中華鍋に用いられることの多い竹ブラシです。
家庭での鉄フライパンの洗浄には少し長めに感じられるかもしれませんが、熱を持ったまま洗うことの多い鉄フライパンの洗浄では少し長めくらいの方が使いやすいです。気兼ねなく使える価格帯であることからもおすすめできます。
管理人のレビュー
一般的な竹ささらです。そのままでは硬く洗いにくいことからも「10分ほど煮る」「束ねられている部分に瞬間接着剤をしみ込ませる」「先端を剪定鋏などで斜めにカットする」などをして扱いやすくすることをおすすめします。
フライパン洗い ブラシ(マーナ)
- 材質:
- 馬毛
- 長さ:
- 25cm
- 重量:
- 80g
柔らかい馬毛のブラシです。
馬毛は耐熱・耐薬品性に優れているため、表面を傷つけることなく優しく洗い上げることができます。鉄フライパンを洗うには心もとなく感じられるかもしれませんが、ある程度育っているフライパンに洗剤を付けて洗う場合にはおすすめできます。
管理人のレビュー
鉄フライパンの扱いに慣れていない場合には竹ささらをおすすめします。しかしほとんど焦げ付かせることがなく育ってきた油膜を傷つけないように洗いたい場合などには重宝します。ある程度の油慣れをしているフライパンであれば洗剤で洗っても問題ありません。
超強力マグネットフック(Sendida)
- 材質:
- ステンレス鋼
- 耐荷重(垂直方向):
- 10kg
- 耐荷重(水平方向):
- 7kg
強力なマグネットフックです。
フック部分の回転する強力マグネットフックですので、溝やつなぎ目の少ないタイプのレンジフードでも鉄フライパンなどを吊るす(かける)ことができます。耐荷重は「垂直方向10kg」「水平方向7kg」ですので厚板の鉄フライパンであっても安心です。
管理人のレビュー
レンジフードには溝のあるタイプ(ブーツ型)と溝のないタイプ(スリム型)の2種類があります。ブーツ型の場合は溝に掛けるタイプのフックを使えますが、スリム型の場合には超強力なマグネットタイプのフックがおすすめです。