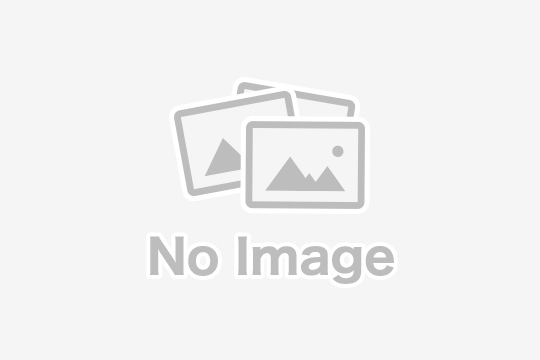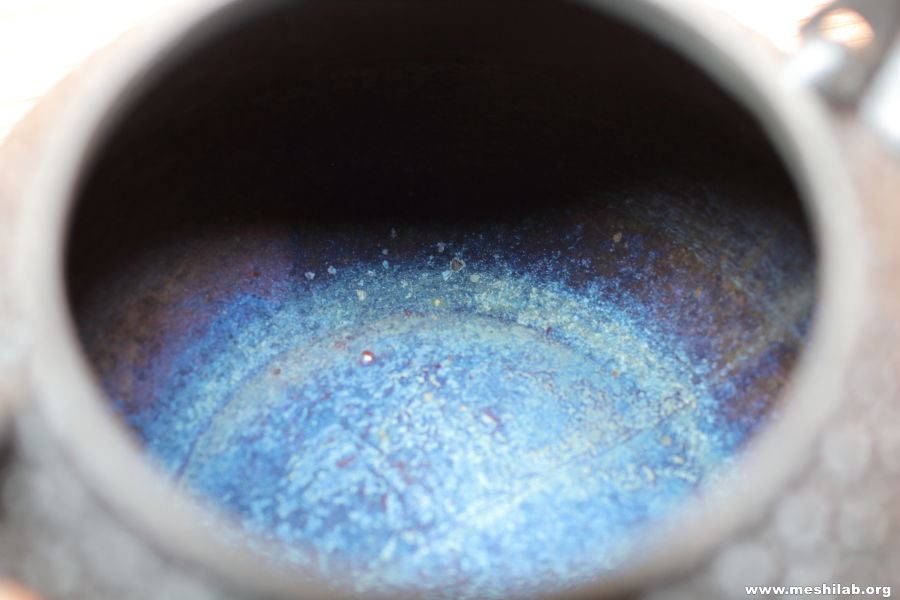この記事は約 4 分で読めます。
こんにちは、めしラボです。
雪平鍋は食材の下ごしらえ(仕込み)に重宝する鍋です。効率的に調理を進めるためには食材の分量に合ったサイズをそろえていく必要がありますので、自ずと数は増えていきます。少人数の家庭であっても15~24cmの各サイズがそろっていると便利です。
私は雪平鍋とやっとこ鍋で各サイズをそろえています。
 めしラボ
めしラボ今回の記事は次のような人におすすめ!
- 雪平鍋のおすすめサイズは?
- 雪平鍋の容量は?
- 大は小を兼ねない理由は?
雪平鍋は16~20cm(15~21cm)の使用頻度が高くなります。
雪平鍋は使い勝手の良い万能鍋です。優れた熱伝導率と熱効率の良い形状によって「お湯が早く沸く」「温度の微調節が容易」「軽くて扱いやすい」などのメリットがあります。このことからもサイズごとに揃えておくと便利です。
はじめは使用頻度の高い16~20cmサイズをおすすめします。
スポンサーリンク
雪平鍋の容量について

雪平鍋の容量はメーカーにより異なります。
たとえば私の使っている谷口金属の雪平鍋(18cm)の容量は1.8Lと記載されていますが、同じ18cmであってもアカオアルミのやっとこ鍋(取っ手と注ぎ口の付いていない雪平鍋)の容量は1.6Lと記載されています。
以下は商品説明欄に記載されている数値です。
| 雪平鍋 (谷口金属) | やっとこ鍋 (アカオアルミ) | |
|---|---|---|
| 15cm | – | 1.0L |
| 16cm | 1.3L | – |
| 18cm | 1.8L | 1.6L |
| 20cm | 2.6L | – |
| 21cm | – | 2.5L |
| 24cm | 3.8L | 4.5L |
容量は調理の目安になります。
たとえばパスタや青菜を茹でる場合、一般的には「食材の10倍量のお湯を必要とする」とされていますので、100gのパスタや青菜を茹でるためには(最低でも)1Lの水を沸かさなければいけないということになります。
食材が150gであれば水は1.5Lになります。18cmの雪平鍋(1.8Lでも数値上はできなくはありませんが)余裕をもって20cm(2.6L)の鍋を使うことになります。
このことからも、はじめは16cm、18cm、20cmの3サイズをおすすめします。
家庭用コンロとの相性について

鍋とコンロには相性があります。
家庭用ガスコンロの場合、鍋底全体に火があたる火加減を強火、鍋底に炎の先が当たる火加減が中火、炎の先端が鍋底と火口の中間になる火加減が弱火、火口部分でのみ小さく付いている火加減をとろ火(蛍火)と呼ばれています。
また、家庭用ガスコンロには左右差もあります。
一般的なガスコンロは左右で強火力バーナーと標準バーナーに分かれています。これによって強火力バーナーには「大きな鍋を使えるがとろ火にできない」、標準バーナーには「大きな鍋では火力が不足するがとろ火にできる」という違いが生じます。
このことからも、標準バーナーで使いやすいのは24cm以下と考えるのが妥当な線です。
大は小を兼ねる?

雪平鍋は各サイズをそろえることをおすすめします。
料理は鍋のサイズにより出来栄えが変わります。たとえば食材に対しての鍋のサイズが大きすぎると「水分の蒸発量が大きくなる」「食材が煮汁に浸かりにくくなる」「火の通りが不均一になる」などの問題が生じやすくなります。
雪平鍋は使用頻度の高いサイズを中心に複数個揃えておくことがポイントになります。
ちなみに雪平鍋は和の調理道具になりますので、SI単位による2cm刻みと、尺貫法による寸(約3cm)刻みのものがあります。個人的には3cm刻みの方が扱いやすいと感じていますが落し蓋などとの相性もありますのでSI単位の方が選択肢は多くなります。
どちらの規格でそろえるかも(一応は)考慮しておくことをおすすめします。
まとめ・雪平鍋のサイズは?
はじめての雪平鍋のサイズには16~20cm(尺貫法の場合は15~21cm)の3サイズをおすすめします。
少人数分の調理であれば3サイズがあれば事足ります。余裕があれば24cmもそろえておくと尚良いかと思います。しかし大型の雪平鍋(片手鍋)は一般家庭の流し台では洗いにくくなりますので、両手鍋ややっとこ鍋(取っ手と注ぎ口のない雪平鍋)も選択肢に入ってくるかと思います。
雪平鍋とやっとこ鍋はそれぞれに良し悪しがあります。
おすすめの関連アイテム
和の職人 深型ゆきひら鍋 18cm(谷口金属工業)
- 材質:
- アルミニウム(アルマイト)
- 板厚:
- 2.2mm
- 重量:
- 0.44kg
標準的な雪平鍋です。
アルマイト加工が施されているので変色しにくく耐食性に優れています。アルマイト加工は長期の使用により傷んできますが、それ以降はボンスターで磨くなどして一般的なアルミ鍋のように使用できます。交換用のハンドルもラインナップされているので安心です。
管理人のレビュー
10年近く使用していますが不満はありません。「蓋を使えない」「料理を入れたままにできない」などを欠点としてあげる方もいますが、これらはこの製品の問題ではなくアルミの雪平鍋全般に言えることですので欠点だとは思っていません。
業務用 TKG 雪平鍋 18cm(遠藤商事)
- 材質:
- アルミニウム
- 板厚:
- 2.6mm
- 重量:
- 530g
ステンレスのハンドルの付いた雪平鍋です。
多くの雪平鍋はハンドルが木製です。そのため「炒め物や揚げ物などによりハンドルが傷む(低温炭化してしまう)ことがある」などの問題がありますが、ハンドルがステンレスであれば気兼ねなく使用することができます。
管理人のレビュー
次に買い替えるとすればこのタイプだと考えています。雪平鍋は食材の下ごしらえに利用されることの多い鍋ですが、きんぴらなどのようなちょっとした炒め物にも重宝されます。標準的な雪平鍋よりもかなりの厚板(t2.6)ですので、料理の仕上がりの面でも期待できます。
DON矢床鍋 18cm(アカオアルミ)
- 材質:
- アルミニウム
- 板厚:
- 3.0mm
- 重量:
- 480g
やっとこ鍋はハンドルのない雪平鍋です。
ハンドルがないことにより炒め物や揚げ物をしても木製ハンドルの低温炭化を心配する必要はありませんし、注ぎ口もないために蓋がきれいにはまります。また比較的安価に厚板(t3.0)のメリットを享受することができます。
管理人のレビュー
一般家庭では馴染みのないやっとこ鍋ですが、ハンドルがないことにより「3口コンロをフルに使っても邪魔になりにくい」「洗いやすいので清潔に管理できる」「重ねて収納することができる」などのメリットがあります。個人的には高頻度で使用しています。
厚手サワラ木蓋 15cm用(雅うるし工芸)
- 材質:
- サワラ材
- 厚さ:
- 約15mm
- 重量:
- 125g
サワラ材の落し蓋です。
木の落し蓋には「煮汁がまわるので味ムラができにくくなる」「食材を押さえつけることで煮崩れしにくくなる」などの効果があります。サワラ材には「吸湿性と放湿性に優れていて水分による変形が少ない」という性質があります。
管理人のレビュー
家庭での落し蓋には紙蓋を利用される方が多いですが、木の落し蓋のような重さがないために食材が踊って煮崩れしてしまうことがあります。各サイズをそろえる必要があるというデメリットはあるものの、そろえる価値はあります。
業務用 ヤットコ鋏 ステンレス(遠藤商事)
- 材質:
- ステンレス
- 長さ:
- 229mm
- 重量:
- 約254 g
ステンレスのやっとこ鋏です。
やっとこ鋏はやっとこ鍋をつかむための道具ですが、その他にも「食材を入れたザルをつかんで湯通しをする」「オーブンや魚焼きグリルからグリルプレートの出し入れをする」などにも使えます。また雪平鍋のハンドルが傷んだ場合にもおすすめできます。
管理人のレビュー
やっとこ鋏には鉄製とステンレス製がありますが、特別な理由がなければステンレス製のものをおすすめします。使用頻度が高く水に濡れることの多いやっとこ鋏は、手入れを怠るとすぐにサビてしまいます。
ガラス蓋 18cm(和平フレイズ)
- 材質:
- 強化ガラス
- 厚さ:
- 全面物理強化ガラス4.0mm
- 重さ:
- 0.35kg
一般的なガラス蓋です。
多くの雪平鍋には蓋を使えません。使える場合であってもハンドルの取り付け部分と注ぎ口部分に隙間が空いてしまいます。しかしやっとこ鍋の場合には一般的なガラス蓋を使用できますので、調理により使い分けられると便利です。
管理人のレビュー
アルミの雪平鍋には料理を入れたままにすることができません。しかし少量の蒸し物や保温をしたい場合にはガラス蓋があると便利なこともあります。このことからもやっとこ鍋を利用している場合にはガラス蓋があると料理の幅が広がります。