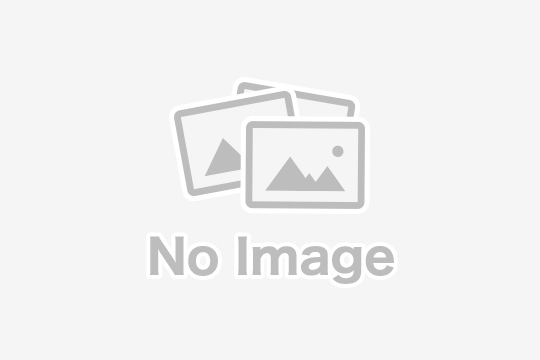この記事は約 4 分で読めます。
こんにちは、めしラボです。
家庭料理にも重宝される雪平鍋ですが、使用方法や食材の特徴によっては変色してしまうことがあります。特にゆで卵などを作ると鍋の内側が黒く変色してしまうことからも「体に悪いのでは?」と心配する方も少なくありません。
多くの場合、雪平鍋の変色はアルミニウムの腐食が原因になっています。
 めしラボ
めしラボ今回の記事は次のような人におすすめ!
- 雪平鍋の変色(黒ずみ)原因は?
- 雪平鍋の変色に体への害はないのか?
- 雪平鍋を変色しにくくする方法は?
雪平鍋(アルミ鍋)は変色します。
一般的な雪平鍋は熱伝導率に優れたアルミニウムで作られています。アルミニウムは食品中の反応成分(酸、アルカリ、卵を調理する際に生じる硫化水素など)により白色、灰色、黒色などに変色してしまうことがあります。
そのためフッ素樹脂加工やアルマイト加工された製品が多くなっています。非アルマイトやアルマイトの剥がれてしまった雪平鍋は変色しやすくなっていますので注意が必要です。
スポンサーリンク
アルミニウムの変色とは?
雪平鍋の変色は酸化物や水酸化物によるものです。
アルミニウムは調理による酸、アルカリ、卵から発生する硫化水素などに反応してしまいやすい金属です。そのためにお酢を使った調理をすると鍋がピカピカになりますし、卵を茹でると黒く変色してしまったりすることがあります。
雪平鍋の変色は大きく2種類です。
| 白色の変色 | 白さび |
|---|---|
| 黒色の変色 | 黒変化現象 |
白色の変色は「アルミニウムと水分が反応して形成された水酸化アルミニウムの色」であることが多く、黒色の変色は「水酸化アルミニウムと水分中の微量物質(ミネラル)が反応したことによる色」であることが多くなります。
そのため軟水の地域よりも硬水の地域の方が変色しやすくなります。
変色に害はあるのか?
雪平鍋の変色に健康への害はありません。
アルミニウムは両性金属(酸とアルカリの両方に反応してしまう金属)ですので調理による多少のイオン化は起こりますが、厚生労働省の示している数値では「すべての調理道具をアルミニウム製に切り替えても問題は起こらない値」になっています。
問題となるのは雪平鍋へのダメージとなる可能性があることです。
本来、アルミニウム(非アルマイト)は自然酸化による酸化皮膜により守られています。この酸化皮膜があるからこそ変色(アルミニウム酸化物や水酸化物など)が起きても腐食が進行することはありません。
アルミニウムは自然酸化により不動態皮膜を形成するということです。
しかしアルミニウムには「塩化物イオンやアルカリ環境には特に弱い」という特徴がありますので、酷い変色が起こるような扱い方(料理を入れたままにしておくなど)をしてしまうと孔食(ピンホール)が発生して穴が開いてしまうこともあります。
これらのことからも雪平鍋を長く使っていくためには注意が必要です。
雪平鍋の黒ずみを落とすには?
黒ずみの落とし方には大きく2種類があります。
クレンザーなどを使って物理的に落とす方法と、酢水などの酸により表面を溶かして落とす方法です。メーカーの取扱説明書や家庭料理の参考書などでは酢水などを煮立たせる方法を推奨していますが、個人的にはクレンザーなどの使用をおすすめします。
物理的に落とした方が手早くきれいに仕上がります。
| クレンザーなど | 物理的に表面を削り落とす |
|---|---|
| 酢水など | 酸により表面を溶かして落とす |
重曹を使用してはいけません。
重曹やセスキ炭酸ナトリウムなどを使った掃除をしている場合には「研磨作用のある重曹を使えばいいのでは?」と考えてしまうかもしれません。しかし重曹は強い塩基性(アルカリ性)ですのでアルミニウムと反応して黒色化が進んでしまいます。
このことからも、クレンザーやスチールウールを使用して落としていきます。
ちなみに研磨力は「クリームクレンザー<クレンザー<スチールウール」の順になりますので、軽度の黒ずみであればクリームクレンザーを使用して重度の場合にはスチールウールを使用するようにします。
変色しにくくするには?
アルミニウムは酸化皮膜により変色しにくくなります。
雪平鍋の酸化皮膜には大きく3種類があります。それが「アルマイト(陽極酸化皮膜)」「自然酸化皮膜」「米のとぎ汁や米ぬかなどを煮立たせることにより形成される酸化皮膜(アルマイトに似た簡易的な酸化皮膜)」です。
雪平鍋にアルマイト加工のものが多いのは酸やアルカリに反応しにくくなるためです。
| アルマイト (陽極酸化皮膜) | 強制的な酸化による厚い皮膜 |
|---|---|
| 自然酸化皮膜 | 自然に形成される薄い酸化皮膜 |
| 米ぬかやとぎ汁などを煮立たせる | アルマイトに似た簡易的な皮膜 |
アルマイトと非アルマイトでは扱いが変わります。
アルマイト加工の雪平鍋は皮膜を維持することがポイントとなり、非アルマイトの雪平鍋は自然酸化や米ぬかなどを上手に利用しながら使っていくことがポイントになります。たとえば、大根の下茹でや豚バラ肉の油抜きなどのように「米ぬかなどと一緒に煮立たせる下ごしらえ」に使っている雪平鍋は自然と変色しにくくなります。
反対に、使い込まれてアルマイト加工がすり減ってしまっている雪平鍋やゆで卵を頻繁に作っている雪平鍋はすぐに変色してしまうことになります。
まとめ・雪平鍋の変色原因は?
雪平鍋は正しく使用していてもも変色します。
雪平鍋はアルミニウムと水分が反応することにより白色の水酸化アルミニウムが形成され、水酸化アルミニウムと水分中の微量物質(ミネラルなど)が結びつくことにより黒色へと変色してしまいます。
変色を防ぐためには酸化皮膜を形成させることがポイントとなり、アルマイト加工、自然酸化皮膜、米のとぎ汁などを煮立たせることで形成される簡易的な皮膜などが利用されています。
おすすめの関連アイテム
和の職人 深型ゆきひら鍋 18cm(谷口金属工業)
- 材質:
- アルミニウム(アルマイト)
- 板厚:
- 2.2mm
- 重量:
- 0.44kg
標準的な雪平鍋です。
アルマイト加工が施されているので変色しにくく耐食性に優れています。アルマイト加工は長期の使用により傷んできますが、それ以降はボンスターで磨くなどして一般的なアルミ鍋のように使用できます。交換用のハンドルもラインナップされているので安心です。
管理人のレビュー
10年近く使用していますが不満はありません。「蓋を使えない」「料理を入れたままにできない」などを欠点としてあげる方もいますが、これらはこの製品の問題ではなくアルミの雪平鍋全般に言えることですので欠点だとは思っていません。
業務用 TKG 雪平鍋 18cm(遠藤商事)
- 材質:
- アルミニウム
- 板厚:
- 2.6mm
- 重量:
- 530g
ステンレスのハンドルの付いた雪平鍋です。
多くの雪平鍋はハンドルが木製です。そのため「炒め物や揚げ物などによりハンドルが傷む(低温炭化してしまう)ことがある」などの問題がありますが、ハンドルがステンレスであれば気兼ねなく使用することができます。
管理人のレビュー
次に買い替えるとすればこのタイプだと考えています。雪平鍋は食材の下ごしらえに利用されることの多い鍋ですが、きんぴらなどのようなちょっとした炒め物にも重宝されます。標準的な雪平鍋よりもかなりの厚板(t2.6)ですので、料理の仕上がりの面でも期待できます。
DON矢床鍋 18cm(アカオアルミ)
- 材質:
- アルミニウム
- 板厚:
- 3.0mm
- 重量:
- 480g
やっとこ鍋はハンドルのない雪平鍋です。
ハンドルがないことにより炒め物や揚げ物をしても木製ハンドルの低温炭化を心配する必要はありませんし、注ぎ口もないために蓋がきれいにはまります。また比較的安価に厚板(t3.0)のメリットを享受することができます。
管理人のレビュー
一般家庭では馴染みのないやっとこ鍋ですが、ハンドルがないことにより「3口コンロをフルに使っても邪魔になりにくい」「洗いやすいので清潔に管理できる」「重ねて収納することができる」などのメリットがあります。個人的には高頻度で使用しています。
厚手サワラ木蓋 15cm用(雅うるし工芸)
- 材質:
- サワラ材
- 厚さ:
- 約15mm
- 重量:
- 125g
サワラ材の落し蓋です。
木の落し蓋には「煮汁がまわるので味ムラができにくくなる」「食材を押さえつけることで煮崩れしにくくなる」などの効果があります。サワラ材には「吸湿性と放湿性に優れていて水分による変形が少ない」という性質があります。
管理人のレビュー
家庭での落し蓋には紙蓋を利用される方が多いですが、木の落し蓋のような重さがないために食材が踊って煮崩れしてしまうことがあります。各サイズをそろえる必要があるというデメリットはあるものの、そろえる価値はあります。
業務用 ヤットコ鋏 ステンレス(遠藤商事)
- 材質:
- ステンレス
- 長さ:
- 229mm
- 重量:
- 約254 g
ステンレスのやっとこ鋏です。
やっとこ鋏はやっとこ鍋をつかむための道具ですが、その他にも「食材を入れたザルをつかんで湯通しをする」「オーブンや魚焼きグリルからグリルプレートの出し入れをする」などにも使えます。また雪平鍋のハンドルが傷んだ場合にもおすすめできます。
管理人のレビュー
やっとこ鋏には鉄製とステンレス製がありますが、特別な理由がなければステンレス製のものをおすすめします。使用頻度が高く水に濡れることの多いやっとこ鋏は、手入れを怠るとすぐにサビてしまいます。
ガラス蓋 18cm(和平フレイズ)
- 材質:
- 強化ガラス
- 厚さ:
- 全面物理強化ガラス4.0mm
- 重さ:
- 0.35kg
一般的なガラス蓋です。
多くの雪平鍋には蓋を使えません。使える場合であってもハンドルの取り付け部分と注ぎ口部分に隙間が空いてしまいます。しかしやっとこ鍋の場合には一般的なガラス蓋を使用できますので、調理により使い分けられると便利です。
管理人のレビュー
アルミの雪平鍋には料理を入れたままにすることができません。しかし少量の蒸し物や保温をしたい場合にはガラス蓋があると便利なこともあります。このことからもやっとこ鍋を利用している場合にはガラス蓋があると料理の幅が広がります。